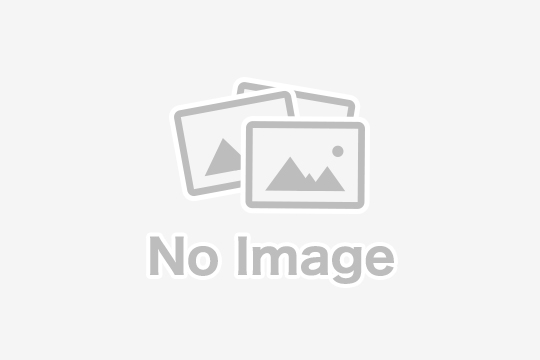文責医師:性別不合(GI)学会認定医 大谷伸久
※本記事は、性別不合・性別違和を専門とする医師が責任を持って執筆したものです。
日本で使うジェンダーは外来語?
ジェンダーは「gender」という日本語の外来語で、本来の意味は、英語で一般的に理解される「2つの性別」として理解されています。社会一般に使われる「性別」と、女性らしく、男性らしくするといった社会に関与する性の役割として暗黙の秩序を指します。
しかし、これら以外では、実際には正確に使用されていません。ジェンダーは、個人情報を必要とする性別欄で使う用語ではありません。このような場合には、生物学的な性と解釈されていますが、じっさいのところ、性別、sex性、gender性の間にきちんとした区別がありません。
Xエックスジェンダーは、性別の意味か?
Xエックスジェンダーは、ジェンダーという用語を含めることによって、外来語のようで、自分の性別が女性でも男性でもないことを示すXとして使われることが多いようです。
表向きの外来語では、Xを「性別」という言葉では使用しません。Xエックスジェンダーは日本以外では使われておらず、日本語独特の用語です。近い言葉は、queer、asexual transgender?
表向きは「性別」と同じ意味を持つものの、日本語の文脈では異なる意味合いを持つ可能性があります。
日本の仮性陰陽、両性具有に関する用語は、「両性」と「中性」があります。さらに良く遭遇する言葉は、「無性」です。
これら3つの用語にはすべてに性という言葉が含まれており、文脈上では生物学的性、性別、あるいは同時に両方と関係があると理解できますが、このとき使う、「性」は、性別なのかジェンダーなのかの区別がありません。中は「中間」を意味し、文字通りに翻訳すると、ミドルセックス、ジェンダーになります。両性は「両方」を意味し、「男女とも」、無性は「性別・性別なし」です。
両性というと、男性と女性の両方の生殖器を所有しているか、男性的および女性的な特性の両方を持っている人を指す傾向があります。中性は英語でいう「アンドロギヌス」と訳され、男性でも女性でもないという意味になります。しかし、インターネットユーザーやコミュニティによるこれらの用語の使用状況によると、いくつかの違和感があります。
両性は、男性を感じる期間もあれば、女性を感じる期間もあれば、男性と女性の両方の属性を持っていると感じる期間を持つという具合です。中立を示すのではなく、アンドロギヌスの外見だけでなく、女性や男性ではなく、どこか中間のどこかを感じることを意味します。
無性は中立の概念にもっと合っているようで、ジェンダーを完全に拒絶している状態です。もちろん、これらの用語の一般的な理解はあるものの、その使用方法は個人によって異なるでしょう。
Xエックスジェンダーの表現方法
Xエックスジェンダーは、しばしばトランスジェンダーのサブグループと考えられており、これは、トランスジェンダーが使用する性別、男性から女性をMTF、女性から男性をFTMと表現するように従って、FtX、MtX、XtXなどの用語を使用します。そのため、Xエックスジェンダー個人が自分の性自認を表現する方法だとわかります。
なお、日本では、トランスジェンダーtransgenderという用語は一般的にはほとんど使われません。その代わりの用語として、性同一性障害(GID)、場合によりMTFの一部をニューハーフ、オカマ、オナベなどと使われてきました。近年、GIDは、これらの用語の中で最も支配的になり、最もよく知られています。
最初の法的に認められた性転換手術は1998年に行われ、2001年にはトランスジェンダーのティーンエイジャー(FtM)を特集した人気テレビドラマ「三年B組金八先生」でこの用語が広がり認知され始めました。それ以来、FTM、MTF、FTX、MTXの用語は、性別の表示方法としてしっかりと定着しました。
queer(クィア)の普及
1996年にqueer(クィア)運動の波に続いて、トランスジェンダーの外来語は、日本で初めて知られるようになりました。ポストモダニズム※にルーツを持つqueer(クィア)の概念とともに、トランスジェンダーの概念が生まれ、このような性自認の形成をもたらしました。
※近代主義を批判し、そこから脱却しようとする思想運動
これは、トランスジェンダーの性自認が過去に存在しなかったということではなく、彼らがそのように呼ばれなかっただけということです。やがてqueer(クィア)という言葉の使用が始まり、現在海外では主に学術・文学界で広く使わていますが、日本ではあまり知られていません。最近では、LGBTQの「Q」として使われ始めるようになっています。
queer(クィア)という言葉は、性自認の用語として見ることができますが、ますますその用語は、自分の性的指向や性同一性を指すように使用されているようです。したがって、queer(クィア)は、特定の性的指向を持たない、バイセクシュアルと区別される2つの性別(女性と男性)を含むようです。このように考えると、性別のqueer(クィア)は、性自認としての男でもなく女でもないXジェンダーと類似しています。
しかし、queer(クィア)という概念が日本では一般的なレベルで普及していないためか、セクシャリティや性同一性の表現もあまり普及していない。queer(クィア)という概念が日本ではあまり普及していないため、セクシュアリティやジェンダーアイデンティティという用語自体、実際には使われません。
GIDは認める一方、男女二分法がより強くなる社会構造
1990年代後半から始まるGIDが社会的に知られるようになると、トランスジェンダーのアイデンティティのフレーミングだけでなく、セクシュアリティにも影響を及ぼしていきました。GIDの重要性は、個人が性別を「変える」ことを可能にする一方で、それと同時に、厳密に男または女の性の二分法を強制することになり、正式に性を変えるための「許可」が必要になります。
それには、手術を受けて肉体的に、精神的に、そして最も重要なことは、目に見える形で、男性か女性かに判断される必要も生じ、社会の期待に従わなければならない状態にさせているとも言えるでしょう。
これはミシェル・フーコーが「バイオパワー 」と呼んだ方法の実践と見ることができるかもしれません。すなわち、集団は規律と繁殖を通してを監視することによって調節されている。GIDの機能は、バイオパワーに従属するものとして、女性と男性の二元的なシステムの遵守を確保するとともに、性差を医学的に治療することにより、診断を得るために必要な行為を通じた規律と権力関係を維持する。
バイオパワー(生の権力):
欧米社会で「生の権力」という新しい権力をいう。
近年、今までの伝統的な権威(権力)の概念では、理解することも想像することも批判することもできないような管理システムが発展しつつある。たとえば、従来の権力においては、臣民の生を掌握し抹殺しようとする君主の「殺すことのできる権力」が支配的であったに対して、新しい「生の権力」は、従来の抑圧的であるよりも、むしろ、住民の生活、生命を公衆衛生によって管理・統制し、福祉国家という名目で形態を変えた社会システム。よかろうと思っていたものが、実はすべてが管理統制された末恐ろしい社会構造。
現代の日本社会は、ジュディス・バトラーが提唱した「異性愛マトリックス」によって特徴付けることができます。このシステムの命令に従わない生き方や性的関係は異常であり、「矯正」を必要としています。
例えば、第二次世界大戦前のドイツや優生思想に従って、去勢や性器の除去は違法でした。このような法律そのものが現在も存在し続けている国があるくらいです。このような性器の除去または再建は、病気として診断されたひとのみが許可されていました。
医療カテゴリーとしてのトランスセクシュアリティは、同性愛のカテゴリーから部分的に性差を排出し、特にその性差を性転換のカテゴリー内に置かれました。
日本におけるGIDの議論の優位性を考慮すると、そして今後提示される議論を考慮すると、Xエックスジェンダーは、GIDもしくはトランスジェンダーの一面として形作られてきており、ホモセクシュアルや男っぽい女、女っぽい男(butch)とはほとんど関係のないと考えられます。
GIDという用語の最近の構成を考えると、GIDが普及する前に、今までに類似の方法が異なる枠で描かれていた可能性があります。GIDはまた、同性愛よりも社会的に認知され、受け入れられるようになってきており、このことは、ジェンダーに関連する性的能力およびアイデンティティが個人的な定着をすることに影響を与えたと理解することができます。